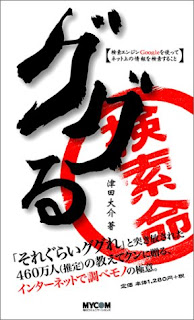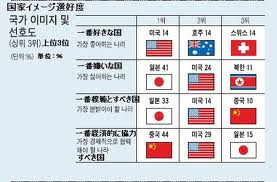2月1日のこのシリーズ(その1)では「小説すばる」の新人賞に私の小説処女作「西97丁目の青春」を応募して、それが見事1次予選を突破し、その後2作目3作目も書き終えそれらを「小説現代」と「オール読物」に応募予定にしている。
というところまで書いた。
では応募1作目が難関の1次予選を突破したことに対してその頃の私の心境はどうだったかを書いてみる。
以前のブログ「小説新人賞・かくも冷酷で厳しい世界」でも触れたが、一般的にこの世界は応募者に対して非情に冷たい一面がある。
そのことは例えば応募者が長い時間をかけ精魂を込めて書いた応募原稿の扱い方に対して特に感じられるのである。
一般的に賞を主催する出版社側は送られてきた応募原稿に対して「受取通知」というものを出さないのである。
もっとも応募者としては原稿が確実に届くように「書留」などを利用して送っているに違いない。
しかしそのようにして送ったとしても当人としては大事な原稿が確実に担当者の元に届いているかどうかは少なからず不安に思うものである。
それもそうだろう。
新人作家を夢見て数ヶ月、あるいはそれ以上の多くの日数をかけて一心不乱に精魂を傾けて書いた大切な原稿なのである。
それに対して受取通知ひとつ出さない出版社の不遜な態度を無礼で冷酷であると思うのは当然ではないだろうか。
しかも数ヶ月先の予選通過の発表に万一自分の名前を見出せなかったらどうだろう。
果たして自分の作品は審査員に正しく読まれ評価されたのだろうか、そうでなく何かの手違いで読まれずに終わったのではないだろうか。
などという応募者の憶測を生む可能性はじゅうぶんあるのだ。
こうした応募者の心情を考えれば受取通知一枚ぐらいは送ってきてしかるべきではないだろうか。
熱心な応募者の一人として私自身はこのことを強く思うのである。
でもこの件はこれぐらいにして、次は私の小説第2作目「編む女」について書いてみよう。
「編む女」という小説は私が前作にも増して力をいれて書いた作品である。
20代半ばの私の実体験をもとに書いたものだが、手前味噌にはなるが大変ユニークな体験だけに、テーマとしては小説にうってつけで、書きようによっては非情におもしろい作品になるのではと並々ならぬ期待を持って執筆に及んだのである。
そして大きな期待をもって「小説現代」への応募に至ったのだが、その結果報告などについては次回にまわすとして、
以下その作品の冒頭の一部分を紹介させていただくことにする。
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
小説「編む女」
「くそっ、あのカップルめ、うまくしけ込んだもんだ」
前方わずか4〜5メートル先を歩いていたすごく身なりのいい若い男女がスッとラブホテルの入口の高い植木の陰に隠れたとき、亮介はさも羨ましそうに呟いて舌打ちした。
「あーあ、こちらがこんなに苦労しているというのにまったくいい気なもんだ」と、今度は随分勝手な愚痴をこぼしながら、なおも辺りに目を凝らしながら歩き続けた。
亮介はこれで三日間この夜の十三(じゅうそう)の街を歩き続けていた。
はじめの日こそ「あの女め見てろそのうちに必ず見つけ出してやるから」と意気込んでいたものの、さすがに三日目ともなると最初の決意もいささかぐらつき始めていた。
時計はすでに十一時をさしており、辺りの人影も数えるほどまばらになっていた。
この夜だけでも、もう三時間近くもこの街のあちこちを歩き回っていたのだ。
「少し疲れたしどこかで少し休んでそれからまたはじめようか。それとも今夜はこれで止めようか」
亮介は迷いながら一ブロック東へ折れて、すぐ側を流れている淀川の土手へ出た。
道路から三メートルほど階段を上がって人気のないコンクリートの堤防に立つと、川面から吹くひんやりとした夜風が汗ばんだ両の頬を心地よくなでた。
「山岸恵美といったな、あの女。城南デパートに勤めていると言ってたけど、あんなことどうせ嘘っぱちだろう。
でも待てよ。それにしてはあの女、デパートのことについていろいろ詳しく話していた。
とすると今はもういないとしても、以前に勤めていたことがあるのかもしれない。それともそこに知り合いがいるとか。
ものは試し、無駄かも知れないけど一度行ってみようか。そうだ、そうしてみよう。
何しろあの悔しさを晴らすためだ。これしきのことで諦めるわけには行かないのだ。
川風に吹かれて少しだけ気を取り戻した亮介は、辺りの鮮やかなネオンサインを川面に映してゆったりと流れる淀川に背を向けると、また大通りの方へと歩いて行った。
「それにしてもあの女、いい女だったなあ。少なくともあの朝までは」
駅に向かって歩きながら、亮介はまたあの夜のことを思い出していた。
とびっきり美人とは言えないが、あれほど男好きのする顔の女も珍しい。
それにやや甘え口調のしっとりとしたあの声。
しかもああいう場所では珍しいあの行動。
あれだと自分に限らず男だったら誰だって信じ込むに違いない。
すでに十一時をまわっているというのに、北の繁華街から川ひとつ隔てただけのこの十三の盛り場には人影は多くまだかなりの賑わいを見せていた。
それもそうだろう。六月の終りと言えば官公庁や大手企業ではすでに夏のボーナスが支給されていて、みな懐が暖かいのだ。
「ボーナスか、あーあ、あの三十八万円があったらなあ」
大通りを右折して阪急電車の駅が目の前に見えてきたところで、亮介はそう呟やくと、また大きなため息をついた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以後次回へ